教育体系設計のポイント①
~経営に役立つ教育体系を設計する~
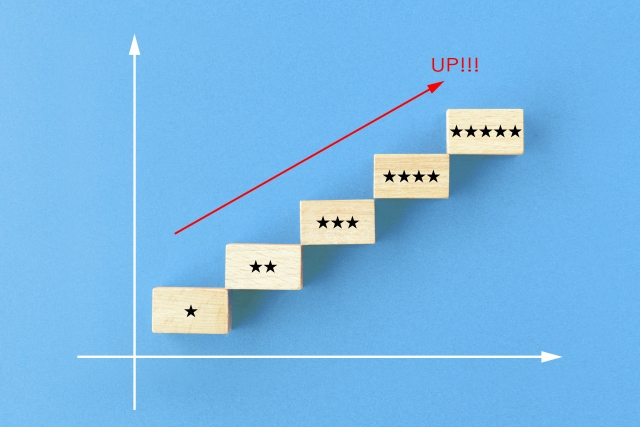;)
経営に役立つ教育体系を設計するためのポイントについて述べます。
【ポイント】
- 経営層から投資を引出す「ザックリ」&「巻き込み」による効果測定を
- 経営目標と教育目標の「つながり」を設計し、実施後の検証を欠かさない
- 受講者上司を巻き込み「研修転移(学んだこと現場で活かす)」を実現する
- 研修転移のカギとなる非人間的要素にも着目せよ
目次
1.経営層から投資を引出す「ザックリ」&「巻き込み」による効果測定を
教育・研修の導入や継続に対し、経営層から投資の許可を得ようとして、教育・人材開発担当者が、効果測定の「正確さ」を追求することは、その理解を得る上でも、コストの観点からも望ましくありません。「ザックリとした効果測定」を、関係者を巻き込んで行うことが、許可を得る上でも、コストの観点からも重要です。
教育・研修の効果測定の目的は経営層に人材育成投資を促すため
研修の関係者(経営層、受講者、受講者の上司等)の中でも、経営層は、研修に「お金を払うか否かを決める」立場にある人たちです。その人たちに、お金を出してもらう、つまり新しい研修を導入する、あるいは現在の研修を継続するためには、研修の効果を納得してもらわなければなりません。この「納得してもらうこと」は簡単なことではありません。
その理由の多くは経営層が、研修の効果測定の方法や結果に対して、なかなか「『うん』と言ってくれない」というものです。 具体的には、人事や人材開発担当者が経営陣から、「それは教育の効果と言うよりも良い顧客にめぐまれたからだろう」とか、「もともと出来が良い人間が参加したからじゃないか」などの反論を受け、「君は教育のせいで成果が出たと言うけど、必ずしもそうは言い切れないのでは・・・」という判断をされ、教育・研修の継続が中止させられたり、あるいは新規の教育・研修の導入が却下されたりということが、よく起こるのです。
教育・研修の効果測定をより正確で、間違いのないものにすることの弊害
効果測定の方法としては、カークパトリックの「レベル4」が一般に良く知られています。
<カークパトリックのレベル4>
- レベル1:反応レベル:良い教育・研修だったか
- レベル2:学習レベル:知識や技術が理解されたか。
- レベル3:実行レベル:学習内容を実行したか。
- レベル4:成果レベル:成果につながったか。
この中で、経営層が求めている研修の効果は、無論、一番下のレベル4です。
上記のパトリックの理論を見ていただければ、すぐお分かりだと思いますが、レベル3,4は、教育・研修中のことではなく、主に教育・研修終了後の現場でのことになりますので、「レベル4の成果が出たのはレベル3の実行のせいである」(もちろんその前提はレベル1、レベル2であるが)と「言い切る」のが、難しくなります。
先ほど述べた、経営層の言葉を借りれば、「確かに実行(レベル3)はあったけど、それ以外にも、彼らはもともと能力が高いという要因もあったので、成果(レベル4)が出たとも言えるよね」と言われてしまうというわけです。
しかし、そういった反論?に応えるために、より正確な効果測定を追及しようと、
- 「では、優秀ではない層にも教育を行い、成果を見てみよう」
- 「違う顧客層を担当している人たちにも受けさせて、成果を見てみよう」
- 「受けていない人たちとも比べてみよう」
などと、効果測定をより正確に行うことに、時間とエネルギーをどんどん割くようになってしまうと、「本末転倒」になりかねません。というのは、いつかは正確に測定できるかもしれませんが、その過程で、正確さを追及するあまり、
- 教育・研修の対象者を、むやみに拡大する。
- 現場の事情を考慮せず、研修に参加させる
- 正確に測定したいがために、現場に負担をかける
上記は、多少オーバーに書いていますが、これでは、「正しく教育の効果測定を行う」ことが目的化してしまい、「成果を上げるためにこの教育を行う」、だから「この教育は成果につながるということを経営層に納得してもらう」という本来の目的が、どこかに置き去りにされてしまいます。
「教育・研修のより正確な効果測定とは?」を追及する学者であれば、このようなコストも、その仕事柄、承認されるでしょうが、企業の実務において、多大な時間やエネルギーを投入し、しかも現場の時間まで使って、より正確な教育の効果測定をすることが、許容されることはまずないと思います。
なぜなら、成果を上げるための唯一の方法が、教育・研修ではないからです。 それが、唯一の方法だとしたら、多大な時間やエネルギー、あるいはお金というコストをどれだけ投入しても良いのですが、そうではないのが、現実だからです
「ザックリ」と「巻き込み」が経営層の納得が得られる効果測定のポイント
「ザックリ」と言うのは、「教育の効果測定などしなくて良い」とか「適当に済ませば良い」という意味ではありません。
むしろ、「経営成果に結びつかない教育」を実施、あるいは継続することは、慎むべきです。より良い教育・研修にしていくためにも、教育・研修の評価を、継続的にきちんと実施していくことが必要です。
そのためも、「より正確な効果測定」に向かって、最初は「ザックリ」でも、それを徐々に、限界はあるが、より正確なものに仕上げていくことが、最も望ましいことなのです。
ただ、繰り返しになりますが、「行き過ぎた正確さの追求」は、かえって企業のためになりません。ある程度の不正確さが残ることは、経営層に、あるいは教育・研修の関係者に、教育の効果あるいは効果測定方法について説明する際には、仕方がないことだと考えるべきです。
よって、例えば、
- 研修終了後の学習事項の実行度合いの調査
- 会社で行っているサーベイ等の結果で研修実施前後の変化を見る
などを行って、教育の効果測定をすることで、説得の材料には、十分になると考えます。
また、私共が現場で多く目にするのが、教育体系の設計や実施方法、あるいはその効果測定方法などが、ごく一部の人で決定されている、つまり、関係者を巻き込まずに、人事や人材開発担当者のみで行われている現実です。 特に「お金を出す立場」の経営層を巻き込まずに、決定されているケースをよく見かけます。
「7つの習慣」でおなじみの、スティーブン・R・コヴィーは、「人間として自分の人生に対して自ら選択し、自ら責任をとる」ことの大切さを述べていますが、これは「自分で選択した場合、誰かのせいにすることが難しくなるため、責任感を高めることができる」ということだと解釈できます。
- 予算を取る時だけ、経営層に教育の効果と測定方法を説明する
- 受講者とその上司には開催を決定した後に、簡単に教育・研修の内容と実施する方法を説明するだけになっている
- 研修後や現場に戻ってからの調査やアンケート時のみ現場に協力を求める
これでは、関係者、特に、お金を出す経営層は教育の効果やその測定方法に、「責任感」を持てません。概して人は、「これは他人のせいで起きた」という心理の時は「批判的」になりがちで、そこから納得を引き出すのは難しくなります。
- 教育内容や実施方法を検討する企画段階から関係者を巻き込む
- 内容や実施方法の検討だけでなく、効果測定方法の検討にも関係者を巻き込む
- 教育終了後の、効果測定だけでなく、その評価、改善にも関係者を巻き込む
といった、いわば「関係者の巻き込み」が、関係者の責任感の醸成し、教育の効果を上げるだけでなく、より納得感の高い、効果測定方法を生み出します。それが結果的に、「完璧で正確な教育の効果測定以外に、経営層を納得させる道はない!」という誤った思い込みからの脱却を、促すことになります。
2.経営目標と教育目標の「つながり」を設計し、実施後の検証を欠かさない
経営に役立つ教育体系創りには、経営者、そして現場を巻き込みながら、経営目標と教育目標の「つながり」を設計し、その実施・検証を行うことが重要です。
経営者が教育・人材開発担当者に対し思っていること
経営者は教育に対して、「すぐ経営成果につながること」を期待しています。百歩譲って、時間がかかったとしても、必ず経営成果につながる教育を望んでいます。しかし、Cristina HallとJohn R. Mattox II(両氏ともGartner社所属の人事コンサルタント)の調査によれば、経営者の多くが、
- 担当者は1つの教育・研修の成功率を測定することに時間を割き過ぎである
- 人材育成が組織化されていない
と言っていると、ATD(Association for Talent Development)が発行している機関紙に寄稿しています。
1つの教育・研修の成功率を重視するのでなく教育・研修を組織化せよ!
これは言い換えると、「経営に役立つ教育を、正しい順番と時間をかけて行え!」という、教育体系を設計する人への、経営者の願いであるとも言えます。Cristina HallとJohn R. Mattox IIは、「教育・研修の組織化(体系化)」とは、具体的には、
- 事業の継続的な成功に最も重要な要因となる「価値」に優先順位をつけそれぞれに、最低レベルと期待レベルで目標を設定する。
- 各教育施策の目標が上記1.とどう繋がるのかを調査し、設計する
という2点を行うことであると述べています。
まず1.の「価値」とは、以下の
- 成長の促進(例えば売上向上、シェアの拡大など)
- 業務の効率化(利益率、利益額の向上)
- 基礎技術の構築と維持
- リスクの軽減
という4つであり、彼らの行った調査結果から、この4つが、最も多くの企業が、経営上重要視している目標であることが判明しました。
また、この4つの「価値」の、各企業における優先順位は、置かれる環境によって、例えば、規制の厳しい業界に属する会社では「リスク軽減」に、株主価値を重視する会社は「利益率の向上」に重点が置かれる、といった違いがあると述べています。
次に2.については具体的には、
成長の促進
▶さらなる売上向上やシェアの拡大につなげるために…
※「顧客の維持・増加」の目標設定
※「プロセス・システム・配置」の改善目標設定
※「製品の改善・開発」の目標設定
を設定し、その達成のためのスキル・知識の習得、及び知識移転の教育目標を設定する。
業務効率の向上
▶さらなる利益率、利益額を向上させるための…
※「成長の促進」と同様の目標
※「生産性向上」の目標
※「コスト削減」の目標
を設定し、その達成のためのスキル・知識の習得及び知識移転の教育目標を設定する。
基礎技術の構築と維持
※持つべきスキルと現状のスキルとのギャップを明らかにし、それを埋めるため、もしくは一定レベルを維持するための教育目標を設定する
例:時間管理、アプリケーションソフト、コーチング、セールス
リスク軽減
※財務リスク回避や、悪評防止など、リスクから、ビジネスを保護するための目標を設定し、そのための教育目標を設定する例:「ポリシー遵守」「業界認定資格取得」「規制や安全訓練の遵守」
というように、「価値(経営目標)と教育目標を関連付けて設計すること」イコール、経営に役立つ教育体系の設計をする中での重要な作業であると述べています。
関係者のエンゲージメントとバイ・インを高め、設計内容を進化させるための2つの質問
さらに、Cristina HallとJohn R. Mattox IIは、「価値の優先順位付けと目標設定」及び「価値に紐づく教育目標の設定と設計」の2つについて、すべてのステークホルダー(経営者、受講メンバーとその上司、及び外部の委託業者等)が、その過程、と結果を共有していることが大切であると述べています。
その共有が、ステークホルダーの「エンゲージメント」(当事者意識)と「バイ・イン」(引き込み)をより引き出し、困難度の高い、「価値の目標(経営目標)」と「教育目標」との紐づけ(関連を設計すること)を可能にするからです。 両氏は、ステークホルダーの「エンゲージメント」と「バイ・イン」を引き出すために、教育体系を設計する者が、ステークスホルダーに向けて行う「2つの重要な質問」というものを挙げています。
- 価値を向上するための目標設定はこれで良いか?
一般的に、価値は「基礎技術の構築と維持」→「業務効率の向上」→「売上・シェアのアップ」「リスク軽減」という「プロセス」になるが、そう考えたときに、4つの価値の向上のためにそれぞれ設定した目標(「何が、いつまでに、どのレベル」)はこれで良いか?という質問です。 - 教育内容や方法と教育到達目標はこれで良いか?
例えば、「このAという研修の内容、方法、目標は狙う価値である『業務効率』を高めるか?」という質問です。
この2つの質問の答えを、ステークホルダー自身にも考えるさせること自体が、関係者の人材育成に対しての「エンゲージメント」と「バイ・イン」をより促し、この質問への答えを、教育体系設計者と一緒になって考え抜くことで、教育体系がより進化していくのです。
そうして、決定した「価値目標の設定」と「教育目標」とのつながりを意識した教育体系の設計を実際に実施し、結果を測定し、改善すべきところは改善し、その結果をまたステークホルダーと共有し・・・というサイクルをステークホルダーと教育・研修担当者と廻し続けていく事が重要なのです。
実質的には、ステークホルダー全員でこのサイクルを廻すことは不可能なので「人材育成委員会」などが、全社の代表として組織され、これを実施していくケースが多いとは思いますが、委員会自体はステークホルダーと十分なコミュニケーションを取りながらその職務を遂行する必要があります。
ステークスホルダーとの共有を図ることイコール研修効果測定にもなる
経営に役立つ教育体系は、元々、それを実施すると、研修後の受講者の変化だけでなく、顧客との関係変化や、現場で起きるリスクの軽減などに及ぶ設計になっています。
ですからその効果を、研修アンケートだけでなく、色々な手段でモニタリングして、その結果をステークスホルダーと共有する必要が生じます。そのモニタリング方法として、「サーベイ」か「アンケート」かというような、手法選びも大切ですが、それらの中身の設計の方がより重要になってきます。
しかし、それとて、従来であれば、教育体系の設計者が一人で悩み、考え、大変な苦労をしていたのですが、この「教育・研修の組織化」という教育体系の設計手法ですと、ステークホルダーと一緒になって考えていくことが出来るので、たいへん効果的・効率的に、それを成し遂げることも出来るようになります。
言い換えると、これがこれからの「教育・研修効果測定のスタンダードなやり方」にと言っても過言ではないと思います。
但し、それには最低限ステークホルダーと設計者間で、「設計内容」は共有しておく必要があります。その際には、「アローダイヤグラム」というツールがひじょうに役に立ちます。「箱」と「→」からなる図で、目標相互の関連がひじょうに理解し易くなるからです。
3.受講者の上司を巻き込み「研修転移(学んだこと現場で活かす)」を実現
研修転移(学んだことを現場に活かす)は、企業が研修を行う目的である、経営成果の達成に不可欠な概念です。それを改善するポイントは、教育・研修そのものよりも、むしろその前後にあります。特に教育・研修前後の、上司の受講者への働きかけを、どう教育体系に盛り込むかが重要です。
学習の転移とは何か
「学習の転移」は、1966年に「ある文脈で学習したことを、別の新しい文脈で活かすことであり、人が社会に適応して生きていくためには、欠かすことができない重要な心的機能である」と、Byrnes(バーンズ)により定義されました。
企業研修においては、「研修で学習したことを如何に現場で活かすか」の機能(研修転移)であり、実施した研修のうち、いったいどれくらいの数の研修が、現場に活かされたかが、「学習転移率」(研修転移率)ということになります。
企業の行う教育・研修の目的は経営成果の達成
「研修転移の理論と実践」(中原淳・島村公俊・鈴木英智佳・関根雅泰共著・ダイヤモンド社)という書籍があるだけでなく、「研修転移」というキーワードで、インターネットで検索をすると、36万件前後ヒットします。
上記の本の中で「研修転移」は、TOT(Transfer of Training)とも言われていますが、「TOT」や「研修転移」という言葉は、今関心の高い「キーワード」であると言えるのではないでしょうか。
「研修転移」…つまり教育・研修で学んだことをどう現場で活かすか?これが着目されている背景には、おそらく、
- 教育・研修の三放し(言い放し、やらせっ放し、現場に任せ放し)では、費用対効果が悪い。何とかしたい。
- 教育・研修で学んだことを、現場に活かし、成果に結びつけることが出来なければ意味がない。良いアイデアはないのか?
という、切実な悩みがあると推察されます。
しかしよく考えてみると、もともと企業が社員に行う教育・研修の目的は、「良い勉強になった」と思ってもらうことではありません。
つまり「学習」が目的ではなく、「学習」したことで、より「成果」を上げる事が教育・研修の目的であるはずです。
何を今さら・・・と感じる方もいると思いますが、経営環境が大きく変わり、黙っていても経営成果が上がるということは無くなった。だから「教育・研修」はどこまでいっても「机上の話」で、「現場とは違う」・・・などと、悠長な事は言っていられなくなったというのが、教育・研修転移への関心の高まりの背景にある、教育・研修担当者や教育・研修関係者の本音ではないでしょうか。
「教育・研修転移率」を左右するのは受講者の上司である
「教育・研修を現場に活かし成果につなげるには?」についての研究は、上述の中原氏主催の「Transfer of Training研究会」や海外のATD(Association for Talent Development)、また九産大の伊藤氏など多くの人が精力的に取り組んでおり、その研究成果は、進化し続けています。
その知見や私共の20年以上の経験から、TOT率を改善するには、以下2つの大きなポイントがあると考えています。ぜひTOT率改善のヒントとして、教育体系の設計に、ご活用下さい。
TOTに大きく影響を与えるのは「職場環境」である
TOTとはTransfer of Training、つまり「教育・研修転移」は、「教育・研修で学んだことが現場で活かされ成果につながるか否か?」のことです。
先の「研修転移の理論と実践」の中でも、受講者の学習結果に大きな影響を与えたのは、
- 受講者がどのような人か
- どのような状況で研修に参加したのか?
- 研修のカリキュラムと構造
であるが、最も重要なものは、「職場環境」であると書かれています。
「職場環境」とは、受講者がどのような上司や同僚に囲まれているのか?どのような仕事に従事しているのか?であり、これが研修で学んだことが実践されるかどうかをかなり左右するというのです。
意外と思われるかもしれませんが、TOTを左右するのは、「研修そのもの以外の要因」であると言えます。教育体系というと、それを考える時に、教育・研修そのものに目をむけがちですが、経営に役立つ教育体系を考える時には、現場まで視野を広げて考える必要があります。
「職場環境」の中でも「受講者の上司」はTOTに大きな影響を与える
1992年にBroadとNewstormは、研修講師にインタビューを行い、TOTに最も影響を与えるのは誰か?またその中で実際に行われているものはどれかを尋ねました。その結果、
- TOTに最も影響力のある受講者への働きかけは上司からのものであった
- しかしらそれはあまり実施されていないという
という調査結果が導き出されています。
つまり、TOTの改善は、環境要因の中でも、とりわけ、受講者の上司の、受講者への働きかけをどう改善するのか?にかかっていると言えます。上司の教育・研修へ参加する受講者の送り出し方、受講後のフォローの仕方等、教育体系の中に、受講対象者の上司をどう取り込むのかが、経営に役立つ、つまり現場で活かされる教育体系を作る上で、ひじょうに大切です。
4.研修転移のカギとなる非人間的要素にも着目せよ
TOTは受講生の上司次第と考えず、現場の使用しているツールや仕組み、あるいは方針などの、非人間的要素にも目を向け、どこを改善すれば転移率が上がるかを考える必要があります。
TOTを左右するのは人的要因だけではない
TOT(Transfer of Training)とは「教育・研修転移」のことで、その意味は、「教育・研修で学習したことが現場で活かされ、仕事の成果に結びつくこと」でした。
また一般的に、その研究結果からTOTを左右する重要な要因として
- 上司の「部下が受ける教育・研修においての学習項目」への支持度合
- 上司が部下に、研修での学習内容を活用する機会・時間を与えるかどうか
- 上司が「部下の研修での学者内容」を日常業務に適合させるか否か
の3つが挙げられることも前述しました。
確かに、TOTは研修・教育受講者の上司がどのような姿勢、アクションをとるかにかかっているといるわけですが、では、職場の上司、あるいは先輩がしっかりしていれば、研修転移は成功すると言えるのでしょうか?
現場の「人」だけでなく、ツールや仕組みと言った、「アーティファクト(非人間的要因)は、TOTの成功を左右する要因にはならないのでしょうか?九州産業大学の伊藤氏が、必ずしもそうではないという、研究論文を発表されています。
※伊藤精男氏のプロフィール
・専門:人間環境学/専攻分野:経営学/研究テーマ:企業組織における人材育成、学習環境のデザイン
・論文/「研修効果の転移条件 アクターネットワーク理論の視点から」(2017)
ANT理論とは何か
科学技術社会論の研究者である、Callon他は1986年に、ANT(Acter Network )理論を発表しました。その理論は、「社会的事象は様々なアクター(Actor)が参加するネットワークで形成される」というものでした。
つまり、社会的事象は、「人」だけでなく「モノ」・「社会」・「技術」・「自然」が、相互に関連を持って存在する状態中で起き、それらはすべて、「自律」したもので、「対等である」とする理論です。
さらに解説すると、例えば、「経理をしているAさん」は一個人で仕事をしているのではなく、Aさんと「パソコン」、「メール」、「筆記用具」、「同じ課のメンバー」とで、仕事をしています。つまり、「経理をしているAさん」はこうした「集合体」として形成され、仕事をしており、このような異種混交のネットワーク(Hybrid Network:ハイブリッド・ネットワーク)が形成されなければ、「経理をしているAさん」たり得ない。という考え方をするのが、ANT理論なのです。
そして、「Aさんの経理能力」を「単にAさんの内側にある属性」と見ず、Aさんの周りに存在する他人(人的アクター)、や自然物・人工物(非人的アクター)と不可分のものと見て、「人の行為や能力」は環境によって変わり、どのような異種混交のネットワークを構成するかにより、その行為や能力発揮の可能性は変わるとする理論でもあります。
よって人の行為や能力を考えるときは、人的アクターのみならず、非人的アクターとの関係も含めて考える必要があるとし、人は他人(人的アクター)が変わっても、自分の行動にその影響を受け、道具(非人的アクター)1つ変わっても、それが人の行動に変化を起こす可能性がある、と指摘しています。
伊藤氏は、我々が、教育体系設計時に、高いTOT率を実現しようと考えるときも、これと同じで、人、つまり受講者の上司が大きな要因ではあるが、それだけでなく、アーティファクト(非人的要因)も踏まえる必要があるのはないか?ということを研究論文で示唆しているのです。
境界的オブジェクト(Boundary Object)とは何か?
境界的オブジェクトとは、StarとGriesemerが、1989年に発表したもので、(少し意訳をすると)異なる環境同士を媒介する「道具」や「仕組み」のことです。
例えば、TOTで言えば、「研修」と「現場」という異なる環境の間で、研修で学習したことを現場で活かすために必要な、道具や仕組み(ANT理論で言う、アーティファクト:非人間的要因)のことと言えます。つまり、境界的オブジェクト次第で、教育・研修で学んだことが現場で活かされ、成果につながるかどうかが、変わってくるということです。
また、StarとGriesemerは、媒介を上手く果たすための、境界的オブジェクトの作成や改善のポイントとして、境界的オブジェクトは、
- 現場の事実(実情)を踏まえたものであること
- 現場の特殊性を考慮したものであること
であるべきだと述べています。
前述の伊藤氏は、境界的オブジェクトも「異種混交のネットワーク」の一部であるので、境界的オブジェクトだけでなく、ネットワークそのものを、「静的」でなく「動的」に捉える、つまり状況や時間軸を踏まえて捉える必要があると述べています。
これはどういう事かと言うと、境界的オブジェクトたるツールや仕組みというのは、新しくて作成しても、人がそれに慣れるのに時間が必要だったり、あるいは、従来からあるツールや仕組みを変えると、戸惑い、煩わしさ等からその活用が進まず、時間や教育を要したりすることがあるということです。
ここまでをまとめると、
- TOTを成功させるには上司といった「人的要因」だけでなく、ANT理論でいう、「非人的要因」にも配慮する必要がある。
- 非人的要因の中でも、「境界的オブジェクト」はTOT成功の鍵を握る。そのためには、境界的オブジェクトを現場の実状、特殊性、時間軸を考慮して作成・改善する必要がある。
ということが言えます。
ANT視点から見たTOTの成功例と失敗例
伊藤氏は、その論文の中で、実践、検証の中からANT視点から見たTOTの成功例と失敗例を挙げています。かなり、具体的な事例ですので、TOTを意識した、経営に役立つ教育体系創りの、参考になると思いますので、ご活用ください。
【成功例】(リーダーシップ研修<アクションラーニング型>)
受講者Aが、サーベイにより自分のリーダーシップの課題がメンバーとの「情報共有」や「共感性」にあると知り、従来の朝礼での一方的指示の改善を決意。
しかし、Aはプレイングマネジャーであるため、全員パートであるメンバーと会話する時間は、外出が多く不可能であった。よって、パートであるメンバーも、限られた時間の中で業務を遂行せざるを得ない事も考慮し、従来からあるパートの業務日報(このケースの境界的オブジェクト)を、「一言コメント」を追記して返却、パートからの返信も可能な双方通行のものに改善し、ねぎらいなども併せて記入するようにと、研修の中で計画した。それを研修後、半年間実践し、課題を克服した。
【失敗例】(営業プロセス改善研修<外部コンサルタント参加>)
一人30件訪問/日という、忙しいルート営業のチームが、既存顧客への御用聞きだけでなく、さらなる売込み、そして、新規顧客先の開拓増を画策していた。
そこで、「提案営業実践研修」を外部コンサルタント入れて実施、営業プロセスの改善を図った。また、単に商品紹介するだけだった営業のアクションが、研修だけで提案型のアクションに変わるとは思われなかったので、TOTを意図して「提案内容の見える化・共有化が出来るシステム」(このっケースの境界的オブジェクト)も導入し、研修後の提案営業の促進を狙った。
しかし、結果的にTOTに失敗した。システムは、訪問件数/日が多いままの中、「手間がかかる」と敬遠され、使用されなかった。また、入力する時間がたとえ出来ても、日々している事は、過去の成功体験に裏打ちされた、「短期決着型商談スタイル」なので、何を入力すれば良いのかが分からず、それも、システムの活用に至らなかった理由となった。
しかも、研修実施やシステム導入に関係なく、「キャンペーン押し込み型の施策」が会社として継続実施されていたことも、提案型営業実践にブレーキをかけ、システムの入力を阻害した。こうして、ANT理論でいうこところの、様々な非人間的要因からの影響を検討せずに導入した新システムは、境界的オブジェクトとして、教育・研修転移としての媒介役にならず、結果TOTに失敗 した。




